

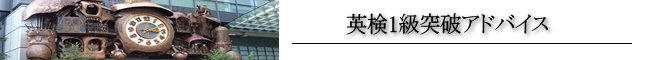
2009年冬の英検1級は、前回の秋の合格点が76点となった難問の反動からか、英検1級の平均的レベルの問題と言えます。まず語彙問題は、解答となる語彙のレベルが比較的低く、レベル1 5000〜8000語水準(基礎語彙) 主に準1級レベルの 比率が約3割、レベル2 8000〜12000語水準(必須語彙) 主に1級レベルの比率が約6割、レベル3 12000語以上(完成語彙) 米国の大学院入試(GRE)レベルが1割となっています。次に読解問題は、難易度は前回ほど高くなくやや難しいレベルで、ここ2, 3回で頻出された理系有利のサイエンス記事問題が無く、世界史に関する問題が2問も主題されているという世界史に偏った点が特徴です。エッセイライティング問題は、「ギャンブルの是非論」という2次試験の頻度2のトピックで、比較的とっつきやすかったと思われます。最後のリスニング問題は、いつもと同じレベルぐらいの問題となっています。よって合格予想点は、ライティング問題のスコアがからくなければ、平均的レベルの79〜80点ぐらいであろうと思われましたが、実際は、予想より2点低く77点でした。これは問題のレベルから考えると、前回の反省から2点ほど受験者にサービスしているかと思われます。アクエアリーズには私が始めて受験した頃の1970年から2010年までの40年間の英検1級の全問題集があり、英検の傾向を過去40年間見て来ましたが、こういった「激励サービス」は10回に1回ぐらいは起こっており、これは英検1級はくじけずに毎回受け続けることが重要であることを物語っています。さてそれではセクションごとに今回の問題を分析していくことにしましょう。
語彙問題分析と攻略法
まず、語彙問題ですが、英検1級に出題される単語は前述の3つのレベルに分けることができ、それらを1000語づつ含むアクエアリーズのボキャビルテキストで、今回のテストに出題された語彙問題21問のカバー率は、19問で 90%です。カバーできなかった2問の内の1問の”detest”はhate よりも嫌悪感が強い場合に用いられる基礎語彙で、過去4回以上選択肢として出題されましたが、今回初めて解答の選択肢として出題されました。そしてもう1つのpurgeはred purge(レッドパージ[赤狩り])世界史用語では日本語になっているので常識語と言えます。出題された21問の語彙問題をレベル別に分けてみると以下の通りです。
レベル1 5000〜8000語水準(基礎語彙) 主に準1級レベル・・・10個出題・48%
detest, ultimatum, indiscretion, insulate, purge, aptitude, liability, morale, intermittently, gullibleレベル2 8000〜12000語水準(必須語彙) 主に1級レベル・・・9個出題・43%
audacity, condone, inscrutable, precarious, misnomer, bolster, deportation, recuperate, defraudレベル3 12000語以上(完成語彙) 米国の大学院入試(GRE)レベル・・・2個出題・9%
renege, banterまた句動詞の方は、アクエアリーズ出版の句動詞1000のテキストのカバー率は4問中4問で100%、また16個すべての選択肢の句動詞のカバー率は12個で75%です。
全体的には、文脈はほとんど無視してコロケーションで解ける問題がほとんどなので、アクエアリーズの『英検1級語彙スーパーボキャブラリー教材』や『発信型英語10000語レベル スーパーボキャブラリービルディング(CD3枚付) 』で、「発信型ボキャビルトレーニング」を実践している人なら全体を5分ぐらいで解いて満点か満点近い点が取れると思います。実際、今回の英検も多くの受講者が満点を取っています。
語彙問題は、NC(no-context型でコロケーションだけで解ける問題)、SC(semi-context型でコロケーションと空所の数語の文脈で解ける問題、FC(full-context型でほとんど全文を読まないと解けない問題)に分かれますが、英検1級の語彙問題の場合、意味・用法・コロケーションの限られたハイレベルな語彙が多いので、運用語彙の豊富な人なら、ほとんど文脈無しでコロケーションで解けるNC、SCタイプの問題が多いと言えます。問題順に見てみると、 1はNC問題で、人を目的語に取るのはdetestとsolicitですが、後者はsolicit 人 for 物(人に物をせがむ)のように使うので、運用語彙力のある人なら前者が正解と分かるでしょう。しかし、SC的にher boss for being rudeでネガティブな文脈から、detest(覚え方は「何でテストよ大嫌い!」)が正解とわかります。同時にsurmount an obstacle(障害を乗り越える)、much-coveted prize(誰もが欲しがる賞)、solicit newspaper contributions(新聞の購読を勧誘する)のコロケーションがすぐに浮かんでくれば、他の選択肢が間違いであることに気づき、自信を持って数秒で解くことができます。
2はfinally gaveとくればultimatum(最後通達)とわかり、3はhave the audacity to+動詞(大胆にも〜する)のフレーズですぐにわかり、4もcondone+犯罪のコロケーションからわかるNC型問題です。5はharmからネガティブな語、つまり2が正解だとわかるSC型。6、7、8、9はそれぞれ、 insulated against, inscrutable expression, precarious position, renege on one’s promiseのコロケーションから即座にわかるNC問題です。9番のrenege onは、映画「ウォール街」でも何回も使われたハイレベル語彙ですが、negative、negateに共通する”neg(否定)”が入っているので類推して欲しいものです。
10の答えであるmisnomerは、過去の英検の語彙問題の選択肢で2回使われ、読解やリスニング問題でも頻繁に登場した「英検1級必須語彙」で、nameが主語なのですぐにわかります。11はdeprive[clear, rob, strip, divest] A of Bと同じ「AからBを取る」のフレーズからもわかります。12、13、14、15、16、17もそれぞれ、have an aptitude for〜(〜の才能がある)bolster one’s position[standing](自分の立場を強化する)、liability to the company(会社にマイナス)、deportation to one’s home country(本国への強制送還)、recuperate from illness[an injury](病気[怪我]から回復する)のコロケーションの知識で解けるNC問題です。また、17は動詞がdropであることからmorale(士気)が、18はmusicが主語であることからintermittently(断続的に)が、19はfriendlyとのコロケーションからbanter(=exchange of teasing remarks[冗談])が、21はtaxpayersとのコロケーションでdefraudが正解であることがわかります。20はFC型で全文を読まないと解けませんが、過去に空所補充の読解問題にも出題された頻出語です。
句動詞問題は、語彙問題ほどコロケーションで解きやすくないかもしれませんが、句動詞の知識がある人なら、22はblot out the sun(太陽を覆いつくす)、23はbarge through the crowd(群衆をかき分けて進む)、25はpin down sb’s stance(人の立場を突きとめる)が合い、その他の選択肢は合わないことがわかるでしょう。24は文脈からclam up(黙りこくる)とわかるFC型問題です。
リスニング問題分析と攻略法
パート1は他のパートと比べて簡単で、合格者の平均はほぼ満点、受験者全体の平均でも10問中8問以上は正解するほどなどで、攻略法は述べる必要があまりないでしょう。このパートが苦手な人は、1日50分の英語のテレビドラマを1本見て「基礎リスニング体力」をつけてほしいものです。でもあまりにもこのパートが苦手な人のために、スコアUPのための選択肢先読み分析法を伝授いたしましょう。つまり「共通事項を探せ」、「confusionを見抜け」です。選択紙を見ると、共通事項は1番は2と4のattend、2番は1(stay away from)と4(avoid)から「避ける対象」なので、そこに待ち構えてフォーカスして聞けばもっと簡単に正解できるわけです。3番は無関係の2を省いて、「栄える」で1,3,4ですが、より限定すると「栄える」+「時」(4は「場所」)となり、4番は1のstricterと4のdiscipliningに共通する「規律に関すること」、5番は「行く」+「誰かと」を表す1と2に絞ることができます。6番は例外的問題でパターン分析対象外ですが、7番は「何らかのプログラム」を表す2と4、8番は「〜のプリンターをゲットする」を表す1,2,3、そして9番は「〜する猶予がある」を表す2と4に絞れ、最後の10番は「〜に〜を求める」では1と2、make concessions, make recommendationsの類似事項では1と4、そして両方に共通する1がより正解になる率が高くなります。こういった先読み・分析にかかる時間は1問30秒で計5分以内にしないといけませんが、このやり方でTOEICのように問題がわかり、答えも絞れるので、前回の英検は放送を聞かなくても9点、今回は6点が取れました。
さて次のPart 2ですが、英検1級の受験者にはこのPart 2が苦手と言う人が多いようですが、このパートは、問題がわかっていて選択肢を先読みする時間もあり、語彙レベルも低いTOEICリスニング問題より数段難しく、平均的受験者が「攻略法」を知らずして高得点を取るのは非常に難しいでしょう。しかし、語彙レベルを高め、攻略法がわかればTOEICと同じように高得点を取ることは可能です。そこで、このセクションが苦手な人のために、スコアUPのための攻略法をまとめると大きく次の5つに分かれます。
3.語彙力をUPしパラフレーズに慣れる 4.背景知識をUPさせる 5.タイトルから解答を割り出す
今回のPart 2の最初の問題の場合、語彙レベルはdeceptive claims, touted as, misleading claims, distort, cynical about~, an essential component of this equationと難しめで、やや複雑な構文レベルからも、聞くマテレベルというより、リーダーズダイジェストや英語圏の高校・大学のテキストのようなレベルの「読み物」を聞くレベルと言った方がいいでしょう。それらの語彙がわからないと日本語のニュースを聞くようにはっきりわかりませんが、ある程度の語彙力、理解力があり、リテンション力の優れた人は話の流れが大体記憶できるので、それらが全部わからなくても問題が解けるでしょう。若い帰国生はこのような力が抜きんでているため、語彙力が乏しくてもカンでやって高得点が取れるわけです。その力が弱い人は、「先読み分析と問題パターンストラトジー」トレーニングをしたり、前述レベルの読み物や放送を多読・多聴する必要があります。
この問題の場合、11番は選択肢の共通点by〜から、何かの「方法」であることが予測できます。また、1か2、3か4のいずれかが答えであることが予測できます。1と2はeducateとinformationから「情報を与える」に関する問題、3と4は「何かを作る」に関する問題であることがわかります。3はnever, every, allを含んだ”categorical answer”なので省き、1か2に絞れます。次に放送を聴きながら、This is known as greenwashing.と「新語」について述べられるとすぐに構え始め、the most commonと「最上級」で言及し始めるとすぐに選択肢に目をやり、focus on and promote a single positive aspect of a product while ignoring any negative onesのパラフレーズ、by limiting the information provided about productsを見抜いて正解を選びます。この問題はキーアイデアでは無くsupporting detailsに関する問題なのでやや難問と言えますが、「最上級」を問う問題が英検のリスニングの頻度1であることを知っていれば楽に対処できます。
12番は選択肢から1か2、3か4に分類できるので、1か2の場合は「顧客のperception」、3か4の場合は「メーカーが作るもの」とポイントを絞ることができ、11番の問題との関連性と選択肢の高度さから前者の可能性が高いことがわかるでしょう。そして放送を聴きながら、How does greenwashing distort consumers’ perception of〜が述べられるや否やそれ以下の英文に耳をそばだてながら、become cynical about〜のパラフレーズ、Customers will mistrust claims about〜を見抜いて正解を選びます。12番も語彙力が要るやや難問と言えますが、これまたこれが起こればこういう状況になるという「因果関係」を頻度1パターンの問題であることが見抜ければ、余裕で対処することができます。
CNNニュースレベルの2つ目のパッセージは、選択肢から13番は3か4に絞れます。ASCの最近の力作である『CD BOOK TOEIC(R)TESTこれ1冊で990点満点』 (アスカカルチャー)にあるように、リスニング問題の攻略法は、「共通項目を見抜け」、「Confusionトリックを見抜け」で、13番はpromotion とemphasis、environmental activismとreduced consumptionが類似しておりその方向性を示しています。それともう1つの攻略法である「タイトルから答えを割り出す」では、タイトルがStoicism Makes a Comebackなので13番はすぐに4が正解であることがわかるでしょう。
3つ目のパッセージはリスニング問題としては、語彙レベルは高いですが、興味深くてわかりやすい内容であるし、何度も繰り返し答えの部分が読まれているので、先読み分析しなくても比較的正解しやすいでしょう。問題予測・分析では15番は共通項目が1のsaw A as Bと2のregarded A as Bから「何かへの見解」、16番は2と3から「何かの益か害」であることがわかり、15番は1か2、16番は2か3に絞ることができます。そして、放送を聴いてからの攻略法は、15番は頻出パターンである「過去と現在の状況の対比」を見抜きます。16番は、sanitize, sterilize, chemical cleaners, rid ourselves of germs, without these germsと何度も述べられているので簡単でしょう。
Part 3のリアルライフリスニング問題は、ここ数年レベルが高くなってきており、今回もトリッキーでチャレンジングな問題が多いようです。まず21番の問題は放送で何度もexchangeと言う語が述べられており、正確に情報をキャッチしないと1を選んでしまうことを予測して作られた典型的なdistracterです。この問題を間違い、きつかったと思う人も多いようですが、これも選択肢先読み分析から答えを2と4に絞ることができます。つまり”get a ticket”という共通事項で、正解はform an orderly lineをline upでパラフレーズした4です。Exchangeを含んだ選択肢は、共通事項もないし、何度も述べられた誤答だと気づかなくてはなりません。22番は、pay a feeの行間を読む必要がありますが、放送を聴きながら誤答にチェックすると同時に正解に丸をつければ簡単です。23番は、これまた1のthe morning rush hour、4のtake the alternative routeとdistracter(トリック)が激しく、正解の部分がパッセージではtraffic is unlikely to clear before 9:30といった具合に「裏返し・行間読みパターン」となっているので、素早く正確に行間を読んで情報をキャッチしないとエラーしてしまいますが、これも先読み分析で、「いつ発つか」のポイントがつかめれば、そこにフォーカスして聞けるので解きやすくなります。24番もやや難問で、情報が紛らわしく正解をキャッチできずエラーしてしまった人もいるかもしれません。でもこの問題も選択肢先読み分析で、全く関連性の無い選択肢1を省き、これは「誰かに連絡する」問題である共通事項を見抜ければ、フォーカスして聞けるので誤答を削除しやすくなります。25番もよくある難問パターンで、2:00 p.m.を午後に言い換え、「2時間前までは飲んでもいい」の「裏返しパターン」を用いて難問にしようとしていますが、選択肢で「飲むのを避ける」という共通事項を示しており、正解を2か4に絞ることができるので、正解を割り出しやすくなります。
パート4のインタビュー問題の攻略法としては、(1)「選択肢先読み分析」(2)「要点メモ取り」が必要となりますが、今回の問題は、従来の選択肢先読み分析法では、正答が予測しにくく、重要ポイントのメモをうまくとることが正答への近道でした。重要な点とは、具体的にはThe best thing is, first of all, と聞こえてくれば、迷わずメモ取り開始で、続くthere’s a high associated with performing, . . . because we really have no idea what’s going to happenから、26番の正答The unpredictability of the genre makes it exciting.が導けますし、最後のinterviewerの質問文 “do the principles of improvisation influence everyday life?” は、以下に重要な内容がきますよ…と聴き手に信号を送っているようなもので、この問いに対する答えの部分Because with improve you have to accept offers, listen to the other person(27番の正答It teaches them to pay more attention to people around them.がわかります)は非常に重要で、迷わずメモ取りをしなければなりません。以上のように要点メモ取りで、容易に正答を見つけることができる問題でしたが、ご参考までに、選択肢先読みアプローチをしてみますと、26番は1のみpositiveで、2, 3, 4はnegativeな選択肢となっており、普通なら共通項目のある2,3,4に正答がある可能性が高いのですが、interviewee (director of the Tokyo Comedy Store)の話す活動や全体のpositiveなトーンから、1のpositive な選択肢が正答であることがわかります。また27番は26番の3のpeopleとの関連から、4のpeopleが正答と見当がつきますが、このように、二つの問題の選択肢をholisticにとらえて、関連を読み取ることも重要な選択肢先読みテクニックといえます。
以上のように英検のリスニング攻略法を述べてまいりましたが、みなさんいかがだったでしょうか。 英検リスニング問題は、パート1では会話文に精通し、パート2ではアカデミックな内容が聞き取れ、語彙力を鍛え、パート3では要点メモ取りができるようになる、という英語学習者にとって、本当に為になる問題構成になっています。最初にも書きましたが、攻略法だけを実行するのではなく、ぜひとも日頃からドラマを見たり、読み物レベルの音声を聞いて、楽しみながらリスニング基礎体力UPに励んでいただきたいと思います。
Let’s enjoy the process!(陽は必ず昇る!)