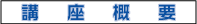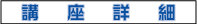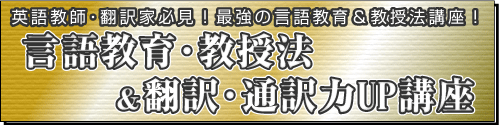
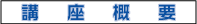
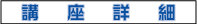
「各々の教育内容について具体的な教育内容をイメージしやすくするため、キーワードを設定した。なお、内容及びキーワードは、日本語教員養成課程において開講される科目等とのマッチングを行う際の目安として記述したものであり、教育内容の諸項目を網羅的に行うことを前提としたものではない。」(文化庁「日本語教育のための教員養成について」より)
|
講座内容(網掛け項目は、日本語教育能力検定試験の出題範囲の「主要項目」に含まれているもの。講座ではできるだけ取り上げる。) | キーワード |
| 言語変種、ジェンダー差・世代差、地域言語、待遇・敬意表現・ポライトネス、言語・非言語行動、コミュニケーション学、コミュニケーション・ストラテジー、など | 語用論ルール、ウチ・ソト、やりもらい、会話のルール、メタ言語、沈黙、意志決定、交渉、根回し、稟議、時間・空間意識、ホンネとタテマエ、人称代名詞・親族名称・呼称、メタファー、発話行為(依頼、言い訳、感謝、約束、謝罪等)、指標、終助詞、など |
| 一般言語学、理論言語学、応用言語学、対照言語学、世界の諸言語、言語の類型、音声的類型、形態(語彙)的類型、統語的類型、意味論的類型、語用論的類型、音声と文法、など | 語族、SOV・SVO言語、モーラ言語、膠着語、パラ言語、非言語、表音・表意文字、タイポロジー、調査・分析法、リサーチ・ツール、リサーチ・クエスチョン、など |
| 日本語の構造:音声・音韻体系、形態・語彙体系、文法体系、意味体系、語用論的規範、文字と表記、日本語史、日本語の系統、など | 音素、アクセント、イントネーション、形態素、語構成、文節、品詞分類、文法、命題、モダリティ、文章談話構造、語用論的機能、位相、など |
| 受容・理解能力、言語運用能力、社会文化能力、対人関係能力、異文化調整能力、表出能力、談話構成能力、議論能力、など | 四技能、葛藤処理(管理)、プレゼンテーション、対人関係構築・維持、関係修復、日本語能力、外国語能力、など |
| 異文化理解と心理:社会的技能・技術(スキル)、異文化受容・適応、異文化間心理学、集団主義、教育心理、など | 異文化理解と心理:カルチャーショック、文化摩擦、判断停止(エポケー)、文化化、自己開示、など |
| 異文化間教育・コミュニケーション教育:異文化間教育・多文化教育、国際・比較教育、国際理解教育、コミュニケーション教育、異文化受容訓練、言語間対照、学習者の権利、スピーチ・コミュニケーション、開発コミュニケーション、異文化マネージメント、など | 異文化間教育・コミュニケーション教育:異文化トレーニング、母語保持、エンパワメント、加算・減算的バイリンガリズム、言語転移、相互学習、体験学習、イマ―ジョン教育、クリティカル・インシデント(危機事例)、カルチャー・アシミレータ、ファシリテータ、など |
| 異文化コミュニケーションと社会:言語・文化相対主義、二言語併用主義(バイリンガリズム(政策))、多言語・多文化主義、自文化(自民族)中心主義、アイデンティティ(自己確認、帰属意識)、異文化間トレランス、言語イデオロギー、言語選択、など | 異文化コミュニケーションと社会:意味付け、コード・スイッチング、翻訳、通訳、バイカルチャリズム、エスノリンギスティック・バイタリティ(ethnolinguistic vitality)、イクイティ(equity)、共生、コンテキスト、異文化交渉、国際協力、など |
| 社会文化能力、言語接触・言語管理、言語政策、各国の教育制度・教育事情、社会言語学・言語社会学、ことばと文化、教育哲学、教育社会学、など | 世界観、宗教観、法意識、自己概念、個人主義、集団主義、公用語、方言、言語生活、外国語・第二言語教育、ピジン・クレオール、ダイグロシア、二言語併用、など |
| 世界と日本:諸外国・地域と日本、日本の社会と文化、歴史、文明、教育、哲学、国際関係、日本事情、日本文学、など | 世界と日本:世界史、日本史、文学、芸術、教育制度、政治・経済、貿易外交、人口動態、労働政策、日本的経営、グローバルスタンダード、社会習慣、時事問題、など |
| 異文化接触:国際協力、文化交流、人口の移動(移民、難民政策を含む)、研修生受け入れ政策、など | 異文化接触:国際機関、技術移転、外国人就労、共生社会、難民条約、子どもの権利条約、国籍、少数民族、ODA, NPO, NGO、など |
| 日本語の構造:音声・音韻体系、形態・語彙体系、文法体系、意味体系、語用論的規範、文字と表記、日本語史、日本語の系統、など | 音素、アクセント、イントネーション、形態素、語構成、文節、品詞分類、文法、命題、モダリティ、文章談話構造、語用論的機能、位相、など |
| 言語理解の過程:予測・推測能力、談話理解、記憶・視点、心理言語学・認知言語学、言語理解、言語学習、など | 言語理解の過程:記憶(エピソード記憶・意味記憶)、スキーマ、トップダウン・ボトムアップ・処理、推論、など |
| 言語習得・発達:習得過程(第一言語・第二言語)、中間言語、二言語併用主義(バイリンガリズム)、ストラテジー(学習方略)、学習者タイプ、幼児言語、言語喪失、学習過程、など | 言語習得・発達:第一言語・第二言語、相互依存仮説、帰納的・演繹的学習法、言語転移、意味フィルター、発達障害、学習障害(LD)、言語病理、沈黙期、など |
| 言語教育法・実技(実習):実践的知識・能力、コースデザイン(教育課程編制)、カリキュラム編制、教室活動、教授法、評価法、教育実技(実習)、自己点検・授業分析能力、誤用分析、教材分析・開発、教室・言語環境の設定、学習者情報、ニーズ分析、など | 言語教育法・実技(実習):教室研究(クラスルーム・リサーチ)、アクションリサーチ、グループダイナミクス、ドラマ、ロールプレイ、スピーチ、ディベート、ディスカッション、多言語・多文化、インタラクション、教師の自己研修(ティーチャ―・ディベロップメント)、コミュニケーション・テスト、アセスメント、ポートフォリオ、シラバス、レディネス、など |
| 言語教育と情報:データ処理、メディア・情報技術活用能力(リテラシー)、マルチメディア、学習支援・促進者(ファシリテータ)の養成、教材開発・選択、知的所有権問題、教育工学、システム工学、など | 言語教育と情報:教材、教具、メディア、コンテンツ、ネットワーキング、視聴覚情報、言語コーパス、CAI・CALL・CMI、衛星通信、著作権、など |
| 世界と日本:諸外国・地域と日本、日本の社会と文化、歴史、文明、教育、哲学、国際関係、日本事情、日本文学、など | 世界と日本:世界史、日本史、文学、芸術、教育制度、政治・経済、貿易外交、人口動態、労働政策、日本的経営、グローバルスタンダード、社会習慣、時事問題、など |
| 異文化接触:国際協力、文化交流、移民、難民政策、研修生受け入れ政策、など | 異文化接触:国際機関、技術移転、外国人就労、共生社会、難民条約、子どもの権利条約、国籍、少数民族、ODA, NPO, NGO、など |
| 日本語の構造:音声・音韻体系、形態・語彙体系、文法体系、意味体系、語用論的規範、文字と表記、日本語史、など | 音素、アクセント、イントネーション、形態素、語構成、文節、品詞分類、文法、命題、モダリティ、文章談話構造、語用論的機能、位相、など |
| 日本語教育の歴史と現状:日本語教育史、日本語教育と国語教育、言語政策、日本語の教育哲学、日本語及び日本語教育に関する試験、日本語教育事情:世界の各地域・日本の各地域、教員養成、学習者の多様化、学習者の推移、各国語試験、など | 日本語教育の歴史と現状:第二次世界大戦、国際共通語、日本語教員養成講座、留学生、就学生、技術研修生、中国帰国者、難民、出入国管理及び難民認定法(入管法)、地域の日本語教育、日本語教育能力検定試験、日本語能力試験、ジェトロビジネス日本語能力テスト、ACTFL、TOEFL、TOEIC、英検、など |
| 異文化接触:異文化適応・調整、児童生徒の文化間移動、外国人児童生徒、帰国児童生徒、留学生政策、地域協力、精神衛生、など | 異文化接触:出入国管理、カウンセリング、など |
| 日本語教員の資質・能力 |
| 言語の構造一般:日本語学 日本語の構造:日本語の系統、音声・音韻体系、形態・語彙体系、文法体系、意味体系、語用論的規範、文字と表記、日本語史、など(上記の通学講座で取り上げきれないものを含む) | 日本語の構造:南方、北方説、音素、アクセント、イントネーション、形態素、語構成、文節、品詞分類、文法、命題、モダリティ、文章談話構造、語用論的機能、発話行為、位相、待遇表現、方言、性差、など |
| 異文化理解と心理:日本語教育・学習の情意的側面、日本語教育と障害者教育、など 言語教育法・実技(実習):目的・対象別日本語教育法、地域別・年齢別日本語教育法、など |